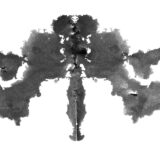今回は人工知能とメンタルヘルスとの関わりについて、全2回に分けて力説します。筆者の「メンタルヘルスの近未来予想図」を共有させていただく機会としてご覧いただければ幸甚です。
現在の精神科医療の課題
精神科受診に関する課題のコラムでも解説いたしましたが、筆者がメンタルクリニックで診療をしていると、こんなフレーズをよく患者さんから伺います。
「メンタルクリニックに行く基準や判断がわからなかったので、ギリギリまでがんばってしまった」
「メンタルクリニックがどういう診療をしているのかわからなかった」
「(メンタルクリニックがどういうところかわかっていれば)もう少し早く来ても良かった」
「そもそもどうしたらいいかわからなかった」
これらは、まだまだメンタルヘルスに対する敷居の高さを物語っています。
実際に精神科受診率について調査した大規模な疫学研究が、2013年から2016年に行われました。日本全国の2500名弱の方々が対象です[1]。
それによると、今まで生活に支障をきたすほどの精神症状を経験した方のうち、医療機関に受診した方は30%程度にとどまっているということが明らかになっています。つまり、70%の方は精神症状に苛まれているにも関わらず何らかの理由で未受診である、ということです。
もっとも、未受診の70%の方の重症度については(文字通り未受診なので)わかりようがなく、心理療法や薬物療法などの介入がどの程度必要だったかは知る由もありませんし、その後どうなったのかも調査する術がありません。
相談の意向はあるのに受診できていない
では、未受診の方々はそもそも受診することに消極的なのでしょうか?
これについても同じ疫学研究から別の興味深い事実が判明しています。
今まで生活に支障をきたすほどの精神症状を経験した方のうち、未受診の方に絞って見てみると、約7割の方がこころの問題で専門家への相談を「絶対に」または「おそらく」受診すると答えています。
これは、受診の意向があるのに行けていない方が精神症状経験者の53%いる計算になり、筆者はこれを最初に読んだ時に純粋に驚きを隠せませんでした。
同時に、疫学調査が示した「現実」が、筆者のもとを訪ねてきてくださった患者さん達の「現場の声」と整合性があることにも「社会的課題」を感じたわけです。
こうした筆者の原体験と疫学調査結果を考慮するに、来院する患者さん側から考えると
- どういう状態が精神的健康でどういう状態になると不健康ないしは病気と捉えるのか
- どのような状況になったら受診するべきなのか
- メンタルクリニックではどのような治療が行われているのか
がより明らかになると、治療的にも予防的にも何か光が見えてきそうだ、と考えるに至りました。
これら3つの課題に共通するのは、根本的な医師の業務である「診断と治療」が鍵を握っている、ということがおわかりいただけると思います。
「正確な」診断と治療方針の策定が医師の仕事
医師は患者さんに対して、problem-oriented と称するいわゆる「問題指向型」のアプローチを典型的な手法として日々診療をおこなっています。その中で、Subjective: 主観的所見、Objective: 客観的所見、Assessment: 評価、Plan: 診断と方針の頭文字をとったSOAPという方法で情報の整理を行い、問題リストを抽出していきます。
「我々医師がexclusiveに役割と責任を担うのは、PLANである。Subjectiveは患者さんが、Objectiveは家族が、Assessmentは技師さんがやってくださる」
と筆者は研修医の時に教わりました。このPlanについて、「『診断と治療』が医師の仕事である。もっと厳密に言うと、診断が正しくないと治療に結びつかない」と言われ、正しい診断をつけることの重要性にフォーカスすることを習いました。
もちろん、Plan以外の、S-O-AいずれもPlanのために必要不可欠であることは言うまでもありませんが、私たちが医療で日々研鑽を積むことの究極的な到達点は、診断の正確性にあるというわけです。
この「正確な診断」について、医師はいつまでも最終的な「診断」を下す立場にはあり続けるけれども、その接頭辞としての「正確な」診断をアシストするのは医師ではなくテクノロジーになってきています。
ところが、精神疾患に関しては、まだまだこの限りではありません。現在の操作的診断や「内因、外因、心因」といった伝統的診断を越える再現性の高い診断方法が望まれる一方で、何らかのブレークスルーが必要になることが、正確な「診断と治療」に不可欠であると筆者は考えています。
さらに拡張して、メンタルヘルス領域が特に目指すのは、これらが担保された上で、さらに先の「患者さんが安心できる」診療に専念できるようにすることでしょう。
我々の想像を越えた医療体験へ
医療には「知識(=WHAT)」の部分と「技術(=HOW)」の部分があります。知識は勉強によって、技術は経験によってそれぞれ身につくものです。知識に関しては、大方テクノロジーによる置き換えが完了しており、現在はこの知識(WHAT)をどのように使いこなすかというHOWの時代です。このHOWの習得は人工知能が得意としており、医療、特に診断における「技術」もじきに置き換わるでしょう。これは、医療の再現性が一段と高まることを意味します。
さらに先の将来、WHATとHOWがなぜ(=WHY)行われるのかという、目的指向性、つまり意識や認知まで人工知能は明文化できるようになると言われています。このHOWこそが、非常に奥深い議論になると筆者は考えています。シンギュラリティ、倫理、哲学、宗教、認知や意識といった概念ともつながってきて、現在ある学問の再編や新しい学問領域も出てくるかもしれません。
精神医学の領域においては、意識や認知の明文化が進むことにより、統合失調症の基本概念である自我障害のモデルや、大脳辺縁系による不安のメカニズムのさらなる解明、精神分析的な意識・前意識・無意識のモデル化と神経症圏の病態シミュレーション、認知行動療法の生理学的なプロセスの可視化などに光が見えてくるかもしれません。
このWHYになってくると、筆者の空想が多分に入ってしまうのですが、少なくとも現行のHOWが医療社会にもたらす貢献は非常に多岐にわたるのは確実です。
医療行為という実務的なレベルから、予防医学という公衆衛生的なレベルまで様々なメリットやコスト削減をもたらすでしょう。
こうした変化は単なる「効率化」とか「業務量軽減」といった目先の変化(これも、医師不足の観点では大変重要ですが)だけでなく、医師がほんとうの意味で患者さんと接する時間をつくることを可能にし、患者さん良し、医療従事者良し、社会良しの「三方良し」の好循環が生まれることを筆者は期待しています。
[1]川上憲人ら 『精神疾患の有病率等に関する大規模疫学調査研究(世界精神保健日本調査セカンド)』2016
・Goldberg D. et al. Common mental disorders-A bio-social model. 1993
・水野雅文ら編 『一般診療科医と精神科医のメンタルヘルスハンドブック』東京都福祉保健局